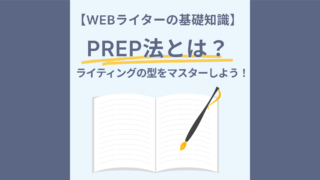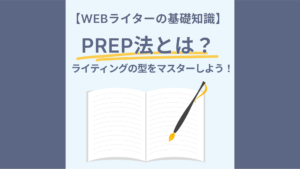【WEBライターの基礎知識】SDS法とは?PREP法とセットで覚えよう!
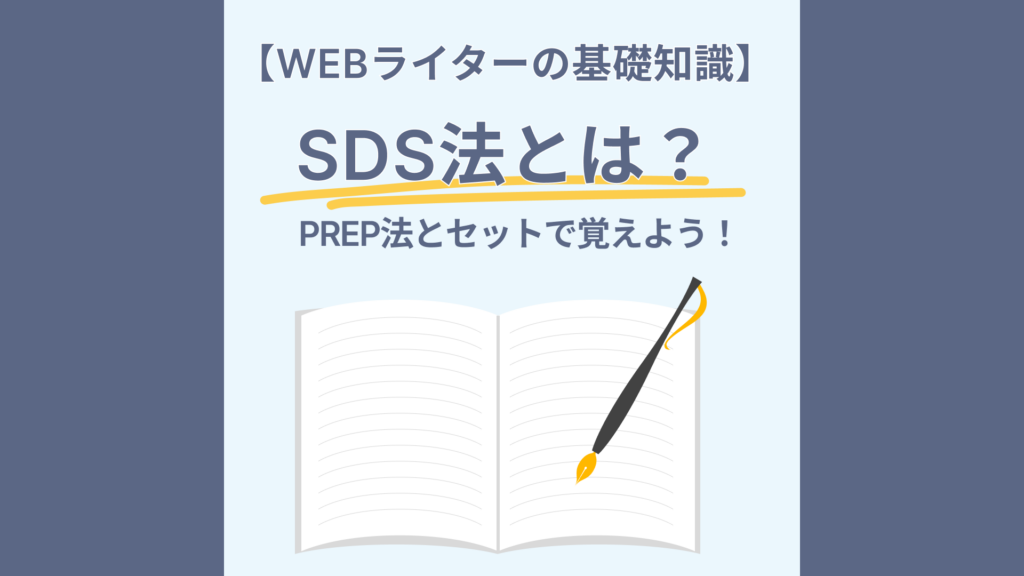
「SDS法ってどんな書き方?」
「PREP法と何が違うの?」
こんな疑問を解消します。
SDS法は、WEBライティングの型のひとつです。WEBライティングのスキルを伸ばそうとすると、「PREP法」「SDS法」のふたつの書き方を習得することは必須となります。(PREP法についてはコチラ)
この記事では、SDS法の書き方やPREP法との使い分けについて解説します。
SDS法を理解して、文章をスラスラかけるようになりましょう!
SDS法とは?
SDS法とは、WEBライティングの書き方(テンプレート)のひとつ。
S:Summary(要点)
D:Details(詳細)
S:Summary(要点)
この順で書いていくことで、文章を書く際に悩みがちな「何から説明したらいいのか」「どのような順番で進めていくとわかりやすいのか」をしっかり押さえることができます。ライティングの「型」を習得することで、文章のクオリティもスピードも高まり、読まれやすい記事を作ることができます。
読者に離脱されないためには、わかりやすく読みやすく書く技術が必要です。「わかりにくい=読者は即離脱する」ということが大前提としてある点を理解しておきましょう。
PREP法とSDS法はどう使い分けたらよいのか
詳しく説明したい時はPREP法
PREP法もSDS法も、最も言いたいことから書き始めて、最後にもう一度言いたいことで締めくくる構造を持っています。
では、それぞれ何が違うのかというと「どれくらい深く理解してもらえるか?」が違います。
PREP法は、
Point:要点
⇒Reason:理由
⇒Example:例
⇒Point:要点
この順番で説明します。
実例や活用例を踏まえて説明することで、読者に「じゃあ、自分の場合はこう考えたらいいのか」と、自分に置き換えて考えやすくなります。なぜそうなのか納得するために必要な手順をしっかりと踏むスタイルがPREP法です。
コンパクトにまとめたいときはSDS法
SDS法は、
Summary:要点
⇒Details:詳細
⇒Summary:要点
この順番で書いていくため、PREP法に比べてコンパクトにまとめることができます。
何かの解説をする場合、何でもかんでも例が挙げられるわけではありませんよね。場面によっては「いや、そこで例を出されてもね…」というときもありますし、各見出しでさんざん例を出していたら「くどすぎない?」と思われたりすることもあるので、バランスが大切です。
また、一つの見出しのなかでいくつもの機能や役割を説明する場合、それぞれを深掘りすると膨れすぎてしまうこともあります。そんな風に、いちいちPREP法でまとめようとすると、ごちゃついてしまって読みにくくなってしまいます。「この見出しでは概要だけ伝えておいて、後で詳しく書こう」という場面でPREP法を使おうとすると、かなりしんどいです。
そんな場合は、SDS法を使うことで、深入りしすぎずスッキリまとまります。
ライティングで大事なのは「わかりやすさ」
SDS法やPREP法は、WEBライティングをするうえで不可欠です。WEBライターをやりたい、もっと早く書けるようになりたい、という方は、しっかりと押さえておきましょう。
このふたつの書き方を意識しながら実践を積み重ねていくと、自分の中で自然と説明の流れが掴めるようになります。一度自分の中に落とし込めば、自然と指が動くようになり、読者にとって読みやすい文章が自然と書けるようになります。
はじめはうまくいかなくても、繰り返し意識することで必ず身に付くスキルですので、ぜひPREP法とSDS法をライティングに役立ててください!
投稿者

-
愛知県一宮市在住のWEBライター。
専門ジャンルはECモールやECサイト、WEBデザインとジュエリー。
5年くらい毎日「ダイエットしなきゃ」「猫飼いたい」「AIと仲良くしたい」と思っています。
夫とストゼロと美味しい食べ物が大好き。